一二三神示 第十巻 水の巻

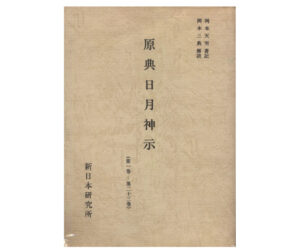
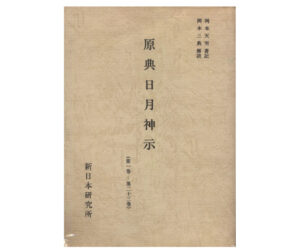
水の巻 第一帖
み◉の巻書き知らすぞ
見渡す限り雲もなく 富士は晴れたり日本晴れ 海は晴れたり日本晴れ
港々に◉の丸の旗 翻る◉の国
それまでに言に言われん言あるなれど頑張りてくだされよ
水もなくなるぞ 天子様おろがみてくれよ
天子様は神と申してあろが なあまだ分からんか 国の神大切せよと聞かしてあろが
◉様にお灯石ばかり供へてはまだ足らぬのぞ お灯石と共に水捧げなならんのざぞ
火と水と申してあろ 筆よく裏の裏まで読みてくだされよ 守護神殿祀りてくれよ
纏わらねば力現れぬぞ 守護神殿は柏手四つ打ちておろがめよ
元の息神様には水がどうしてもいるのざぞ 火ばかりでは力出ぬのざぞ 分かりたか
曇りなく空は晴れたり
元三月十日 水のひつく◉
水の巻 第二帖
ひふみ祝詞であるぞ
全宇宙に神住り栄す 神霊嬉神霊美の御命以て
皇祖親神 誘喜の尊
尽の日迎の立花の音のあやきはらに
身解き祓ひ給ふ時に成りませる祓ひ戸の大神達
諸々の禍事罪穢を
祓ひ給へ清め給へと申すことの由を
天つ神国つ神 八方宜つの神達共に
天の斑駒の耳ふり立てて聴こし召せと
畏み畏みも申す
天のひつくの神 護り給へ幸はへ給へ
天のひつくの神 やさかましませ弥栄ましませ
一二三四五六七八九十
元三月十日 水のひつく神
水の巻 第三帖
◉の子は◉としての自分養ことも務めの一つであるぞ
取り違いすると大層なことになるから気つけておくぞ
書かしてあるご神名はご神体として祀りてもよく お肌守りとしてもよいぞ 皆に多く分けてやれよ
ご神名いくらでも書かすぞ その用意しておいてくれよ ◉急ぐぞ
祓ひ祝詞書き知らすぞ
翔けまくも賢き誘喜の大神様
尽の◉向の立花の音のあやきはらに
身解き祓ひ給ふ時に成りませる
月たつふなとの神 道のなかちはの神
時おかしの神 わつらひの氏の神
巷の神 あきくひの氏の神
大き栄るの神 大きつなきさ日子の神
おきつかひへらの神 へさかるの神
へつなきみ日子の神 へつかひへらの神
闇まかつ日の神 大まかつ日の神
神治日の神 大御治日の神 ひとつの目の神
底つわたつみの神 底つつのをの神
中つわたつみの神 中つつのおの尊
上つわたつみの神 上つつのをの尊
祓ひ豊柱の◉たち共に
諸々の禍事罪穢を祓ひ給へ清め給へと申す言を
聴こ治せと拝み拝みも申す
月に受け日の言葉知らすぞ
ご三体の大神様 ご三体の大神様
日月の大神様
国常立の大神様 豊雲野の大神様
月の大神様 素盞嗚の大神様
あめの神様 かせの神様
いはの神様 あれの神様 ちしんの神様
きの神様 かねの神様 日の神様
日の出の神様 龍宮ノ音姫様
八方宜つの息神様
殊に五十鈴に栄す天照皇大神宮様
豊受の大神様をはじめ奉り
世の中の息神様 産土の大神様の御前に
広き温つきご守護のほど有難く 尊く
恩礼申し上げます
この旅の岩戸開きには千万弥栄のお働き
願い上げます
天地の与 弥栄に栄へまさしめ給ひ
世界の在りとある神民一日も早く
改心致しまして 大神様の御胸に添ひまつり
大神様の御心の間に間に
◉国成就のため働きますよお守り下さいませ
その為この霊この身は
何卒如何様にでもお仕ひ下さいませ
御胸の間に間に
誠の◉国の御民としての務めを努めさして頂くよ
無恥うちご守護下さいませ 神惟霊地はへませ
次に御先祖様の拝詞知らすぞ
惟の身霊宮に神鎮まります遠継祖の神
代々の親神達の御前
また家族親族の身霊の恩前に謹み敬ひも申す
惟の内には諸々の曲言罪穢れ荒し召す
世の守り日の守りに守り咲き広ひ給ひ
誠神国の御民としての務めを全とせしめ給へ
世の守り日の守りに守り捧くるものの絶間無き
子孫の弥栄継きに栄へしめ給へと
拝み拝み申す 神惟霊地ははへませ
一本の草木でも干して蓄えておけよと申してあろかな
四月二十三日 水の日月の神
水の巻 第四帖
お宮も土足にされる時が来る お陰落とさんよに気つけよ
勲章もなんにもならん時が来る 誠一つに頼れ人々
二十四日 水の日月神
水の巻 第五帖
外国の言は無くなるぞ
江戸の仕組み元九月五日までに終わりてくれよ 後はいよいよとなるぞ
◉が申した時にすぐ何事も致してくれよ 時過ぎると成就せんことあるのざぞ
桜花 一時に散ることあるぞ いよいよ松の代となるのぞ 万劫変わらぬ松の代となるのざぞ 松の国 松の代 結構であるぞ
この筆声出して読み上げてくれよ くど申してあろが 言霊高く読みてさへおれば結構が来るのざぞ 人間心出してはならんぞ
五月一日 水のひつくの◉
水の巻 第六帖
喜が元ざと申してあろかな ◉国負けるといふ心言葉は悪魔ざぞ 気 大きく持ちて下されよ
島国日本に捉われてくれるなよ 小さいこと思ていると見当取れんことになるぞ
ひ食べよ ふ食べよ 食べるには噛むことぞ 噛むとは神ざぞ
神に供へてから噛むのざぞ 噛めば噛むほど神となるぞ 神国ぞ 神惟の国ぞ かみなから仕事してもよいぞ
青山も泣き枯る時あると申してあろが
日に千人食い殺されたら千五百の産屋建てよ 神誘喜の神の御教えぞ
神嫌ろ身霊は人民も嫌ろぞ
五月二日 水のひつくの神
水の巻 第七帖
みな病気になりていること分からぬか
ひふみ祝詞宣りて治してやれよ 筆読みて治してやれよ
自分でも分からぬ病になっているぞ 早よ治さぬとどにもならんことになてくるぞ
ここの宮仮であるぞ 真中に富士の山造り その周りに七つの山造りてくれよ
拝殿造りくれよ 筆書かす所造りくれよ てんめ休む所造りくれよ
いづれも仮でよいぞ 早よなされよ
松の心にさへなりておれば何事もすくすくゆくぞ
五月四日 水のひつくの神
水の巻 第八帖
鎮座は六月の十日であるぞ 筆書かして丸一年ぞ
筆で知らしてあろが それからがいよいよの正念場ざぞ びくり箱あくぞ
五月四日 水のひつくの神
水の巻 第九帖
富士は晴れたり日本晴れ いよいよ岩戸開らけるぞ
お山開きまこと結構 松の御代となるぞ
元九月八日からお祓ひ祝詞に天つ祝詞の太祝詞 ひふみ祝詞こと入れて宣れよ
忘れずに宣れよ その日からいよいよ◉は◉獣は獣となるぞ
江戸道場やめるでないぞ お山へ移してよいぞ 役員一度辞めてよいぞ また務めてよいぞ
巡りあるから心配あるのぞ 巡り無くなれば心配無くなるぞ
心配無いのが富士は晴れたぞ 富士晴れ結構ぞ
日月のみたみ いづれも富士晴れ心でおりて下されよ
肉体ちとの間であるが 霊は限りなく栄へるのざぞ
金に難渋して負けぬよにして下されよ 金馬鹿にしてはならんぞ
焦るでないぞ 焦ると心配事できるぞ
神が仕組みてあること 臣民がしよとて出来はせんぞ 細工は流々滅多に間違いないのざぞ 見物してござれ 見事してみせるぞ
不和の家 不和の国の捧げもの 神は要らんぞ
喜びの捧げもの米一粒でもよいぞ ◉は嬉しぞ
元九月八日 とどめぞ
六月二日 水の日月の◉
水の巻 第十帖
五大衆ひくり返ていることまだ分からぬか 肝心要のことざぞ 七大州となるぞ 八大州となるぞ
今の臣民に分かるように申すならば
ご三体の大神様とは
天の御中主の神様 高皇産霊の神様 神皇産霊の神様
伊邪那岐の神様 伊邪那美の神様 撞賢木向津姫の神様でござるぞ
雨の神とは 天の水分の神 国の水分の神
風の神とは 支那都彦の神 支那都姫の神
岩の神とは 磐中姫の神 岩戸開けの神
荒の神とは 大雷のをの神 若き雷おの神
地震の神とは
武甕土の神 祓主の神々様の御言でござるぞ
気の神とは この花咲くや姫の神
金の神とは きんかつかねの神
日の神とは 若姫君の神
日の出の神とは 日子頬笑みの神
陸の音姫殿とは霊依姫の神様の御言でござるぞ
この方のこといづれ分かりてくるぞ 今はまだ知らしてならんことぞ
治らす時節近づいたぞ
六月十一日 水の日月◉
水の巻 第十一帖
◉第一とすれば◉となり 悪魔第一とすれば悪魔となるぞ 何事も◉第一結構
かいの返しキざぞ 気が因ざと知らしてあろが カイのご用に係りてくれよ
何といふ結構なことであたかと始めは苦しなれど みなが喜ぶよになてくるのざぞ さき楽しみに苦しめよ
ここと締めつけて目の玉飛び出ることあるのざぞ そこまでに曇りているのざぞ
激しく洗濯するぞ 可愛い子 谷底に突き落とさなならんかも知れんぞ
いよいよ神が表に現れて◉の国に手柄立てさすぞ 神国光り輝くぞ 日本にはまだまだ何事あるか分からんぞ 早く一人でも多く知らしてやれよ
霊磨けば磨いただけ先が見へ透くぞ 先見える神徳与えるぞ
いくら偉い役人頑張りても 今までのことは何も役に立たんぞ
新しき光の世となるのぞ 古きもの脱ぎ捨てよと申してあろかな
誠心になりたならば 自分でも分からんほどの結構出て来るぞ 手柄立てさすぞ
いくら変わりても勝手は通らんぞ 我折りて素直になりて下されよ
これで良いということないぞ いくら努めても努めても これでも良いということはないのざぞ
神の一厘の仕組み分かりたら 世界一列一帯一平になるぞ
枡かけ引いて 世界の臣民人民 勇みに勇むぞ 勇むことこのほ嬉しきぞ
富士はいつ爆発するのぞ どこへ逃げたら助かるのぞという心我義ぞ どこに居ても救者は救と申してあろが
悪き待つ気は悪魔の樹ざぞ 結構が結構生むのざぞ
六月 十一日
水の巻 第十二帖
人間心には我があるぞ ◉心には我ないぞ
我がなくてもならんぞ 我あてはならんぞ
我がなくてはならず あてはならん道理判りたか
神に融け入れよ 天子様に融け入れよ 我無くせよ 我出せよ
建て替へと申すのは 神界 幽界 現界 にある今までのことを 綺麗に塵一つ残らぬよに洗濯することざぞ 今度という今度はどこまでも綺麗さぱりと建替へするのざぞ
立て直しと申すのは 世の元の大神様の御心のままにすることぞ
美光の世にすることぞ 天子様の美威出輝く美世とすることぞ
政治も経済も何もかも無くなるぞ 食べる物も一時は無くなてしまうぞ 覚悟なされよ
正しく開く道場 成り出つ
初め苦し 開き出て 月生る道は弥栄
地 拓き 世 平吹 代 産霊
天地 栄ゆ 始め和の理
世界の臣民 天子様 拝むとき来るのざぞ
邪魔せずに見物致されよ ご用はせなならんぞ
この筆読めよ 声高く この筆血とせよ 栄人となるぞ 天地混ぜこぜとなるぞ
六月十二日 水のひつくノ◉
水の巻 第十三帖
火と水と申してあろかな
火続くぞ 雨続くぞ 火の災いあるぞ 水の災いあるぞ 火のお陰あるぞ 水の災い気つけよ
火と水 入り乱れての災いあるぞ 近こなりたぞ 火と水の御恵あるぞ
一時は◉のことも大き声で言へんことあるぞ それでも心配するでないぞ 無事晴れるぞ
家族幾人居ても金要らぬであろが 主人どしりと座りておれば治ておろが
神国の型残してあるのざぞ 国治めるに政治要らぬぞ 経済要らぬぞ
◉拝めよ ◉祀れよ 天子様拝めよ 何もかもみな◉に捧げよ ◉から戴けよ 神国治るぞ 戦も治るぞ
今の臣民口先ばかりで誠申しているが 口ばかりでは尚悪いぞ 言止めて仕え纏れ 天くり変えるぞ
六月十三日 水のひつくの神
水の巻 第十四帖
今までは闇の夜であったから どんな悪いことしても闇に逃れること出来てきたが 闇のよはも済みたぞ
思い違う人民沢山あるぞ どんな集いでもたいしよはみな思い違うぞ 早よさぱり心入れ替えて下され
◉の子でないと◉の国には住めんことになるぞ 外国へ逃げてゆかなならんぞ 二度と帰れんぞ 外国ゆきとならぬよ根本から心入れ替へてくれよ
日本の国の臣民みな兵隊さんになった時一度にどと大変が起こるぞ みな思い違うぞ
カイのご用はキのご用ぞ それが済みたらまだまだご用あるぞ
ゆけどもゆけども草茫々 どこから何が飛び出すか 秋の空紅蓮と変わるぞ
この方 化に化て残らずの身霊調べてあるから 身霊の改心中々に難しから 今度という今度は天の規則通りビシビシと埒明けるぞ
ご三体の大神様 三日この世を構いなさらぬと この世はくにやくにやとなるのざぞ
結構近づいているのざぞ 大層近づいているのざぞ
この筆読みて神々様にも守護神殿にも聴かせてくれよ
いよいよ天のひつくの神様御懸かりなされるぞ
元五月五日 水のひつく神
水の巻 第十五帖
日の春は一の宮と土壌であるぞ 女は中山ぞ 奥山も造らすぞ
富士火吐かぬよ拝みてくれよ 大難小難に祀り替へるよ拝みてくれよ
食べ物戴く時はよくよく噛めと申してあろが 上の歯は火だぞ 下の歯は水だぞ
日と月と在わすのざぞ 神漏喜 神漏美ぞ
噛むと力生まれるぞ 血となるぞ 肉となるぞ
六月十七日 ひつくの神
水の巻 第十六帖
かいの祀り結構でありたぞ
◉へたけしたヤのみさキご苦労であったぞ
みなの者お山ご苦労であったぞ
みへたさいとかとつつキ ささキアさかわいしもとかむへたけしたかとたヤのさとたかキしんぼ しよだたかたご苦労であったぞ
てんめご苦労ぞ まだまだご苦労あるぞ 霊の宮造りてよいぞ
我のこと言はれて腹立つ様な小さい心では 今度のご用は出来はせんのざぞ 心大きく持てと申してあろかな
六月二十日 ひつくの神
水の巻 第十七帖
かいのご用は気のご用であるぞ 臣民は身のご用務めてくれよ 喜と美のご用であるぞ
美のご用とは体のご用であるぞ 身養う正しき水開いて伝えてくれよ
今までの筆読めば分かるよにしてあるぞ
綺のご用に使う者もあるぞ キミのご用さす者もあるぞ
奥山は男の山に開いてくれよ ご苦労ながら結構な御役であるからご苦労であるぞ
お守りの石 どしどしさげてよいぞ
み◉の巻 これで終わりぞ
六月二十三日 水の日月◉


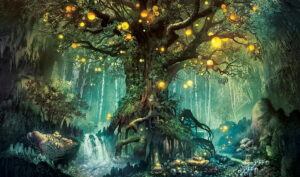
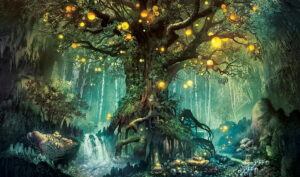
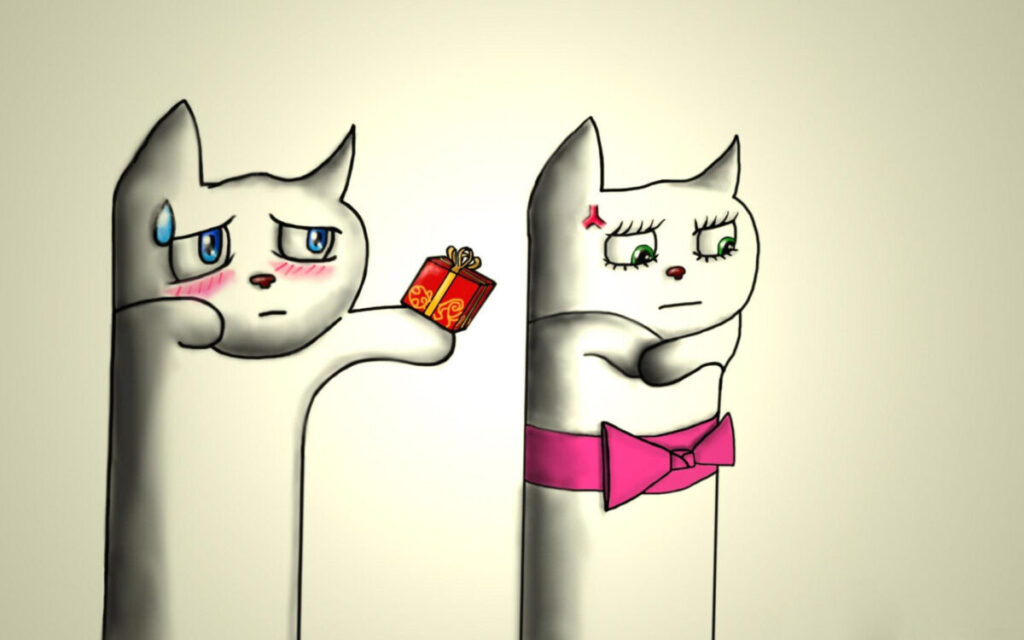
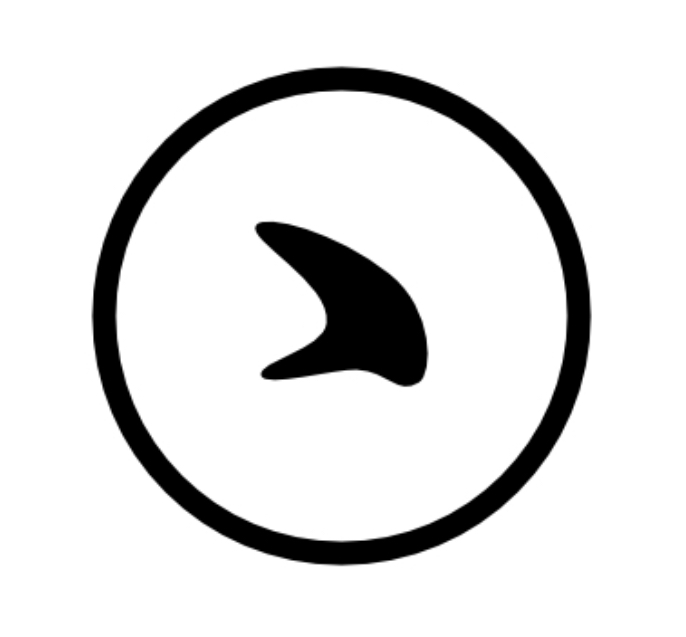


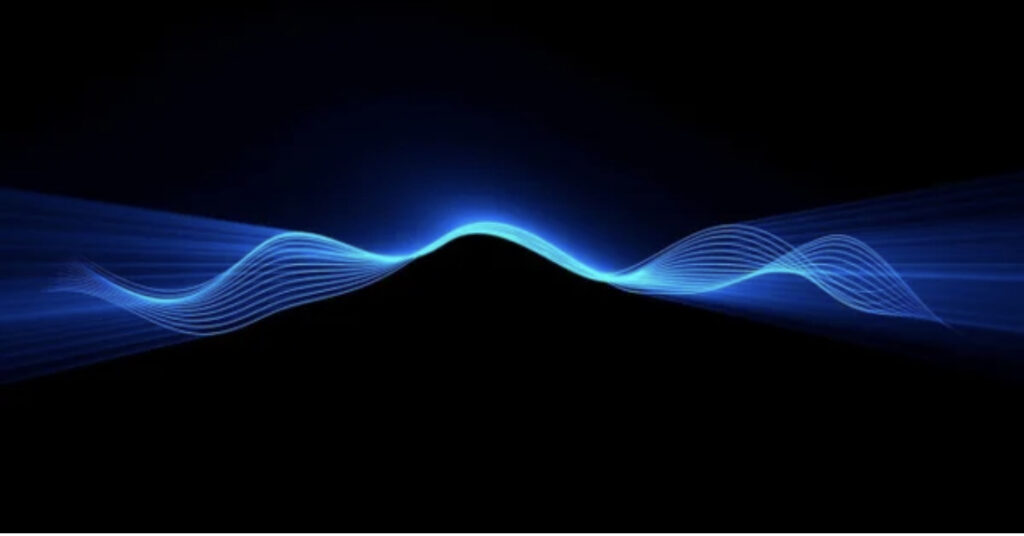

この記事へのコメント